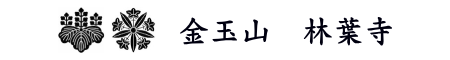林葉寺の歴史
こんにちは。林葉寺です。
林葉寺は、信濃川対岸の天野新田(今の新潟市江南区天野付近)に住んでいた人々の菩提寺として、寛永5年(令和7年、2025年より約408年前)大昌寺8世、海岸春光大和尚を迎え、開山しました。
しかし、20年後の慶安2年頃より、信濃川が鷲ノ木新田から天野方面へと突然流路を変え始めたと言われ、水との戦いが始まりました。そして、開山されて100年、享保13年、林葉寺5世、勧峰玄無大和尚代、ついに水との戦いに敗れ、鷲ノ木新田の住民より土地の寄進を受け、現在の新潟市南区鷲ノ木新田に再建されました。林葉寺は水との因縁が深く、洪水が重なり生産性の低い地域でもあったので、住職が常住する事が少なく、ただでさえ少なかった檀信徒も離れ、お寺として機能しない状況が200年以上も続いたとされていました。
昭和時代に入り、現状を変えるべく本寺である大昌寺様より若い住職が任命され、その方が25世機外順法大和尚であり、後の27世住職である大徹良弘大和尚の実父でした。しかし、良弘大和尚が幼い頃、当時の流行病の為、31歳という若さで他界されました。残された良弘大和尚と実母のキヨは苦労されましたが、大昌寺様より修行僧が何人も手伝いに来られ、お寺としてはなんとか維持する事ができました。
そして、昭和13年9月新潟市大渕(今の新潟市江南区大渕)の本興寺様より得水真龍大和尚が林葉寺に来て下さり26世住職になられました。真龍大和尚尚が住職になられ、林葉寺も少しずつではありますが、復興の兆しが見えるようになっていきました。真龍大和尚は、檀信徒の方々、地域の方々も家族の一員だとおっしゃって何よりも月命日のお参りを大事にされていました。当時は歩きや自転車で一日かけて檀信徒の方々のお宅をまわられていたそうです。
そして、真龍大和尚は誰と接するときも「和顔愛語」(わげんあいご)誰かとと接する時には優しい顔つきで、優しい言葉をかけることを常に心がけ、令和2年1月に亡くなられた27世大徹良弘大和尚、28世 現住職、祖法公彦 副住職、大法悠真も、真龍大和尚の残された月命日のお参りという文化、「和顔愛語」の心を今日に至るまで守り、檀信徒の皆様、地域の皆様に寄り添い、親しみあい、皆が安らぎを感じるお寺を目指し日々精進しております。